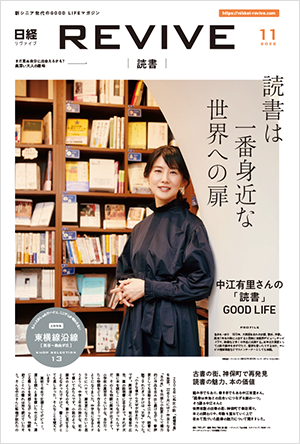じわじわきてます令和の発酵革命
|発酵ブーム再燃|
コラム
GOOD LIFE 総研
posted by 日経REVIVE
よりよく生きるヒント GOOD LIFE 総研
発酵文化の変遷をたどる 編
posted by 日経REVIVE
2025年08月31日

あなたは知っていますか?
奥深い発酵の世界を
そもそも発酵とは、菌や酵母などの微生物の働きによって食品の有機物が分解され、別の物質に変化する化学反応のことです。食品においては保存性、風味、栄養価を高めることが大きな特徴ですが、実際は腐敗と紙一重。微生物の種類と環境のコントロールが要となります。
発酵は大きく5種類に分けられます。最も古い発酵は約1万年前から存在していたといわれる「酵母発酵」です。食品でいうとアルコールやパン。続いて生まれたの
がヨーグルトやチーズ、漬物などの「乳酸発酵」。遊牧民により保存食として発展しました。そして8世紀ごろになるとついに穀物にこうじ菌を繁殖させる「こうじ菌発酵」が生まれます。味噌、しょうゆ、日本酒、甘酒、みりんなど日本の食文化に欠かせない発酵の誕生です。その他、酢などの「酢酸菌発酵」「納豆菌発酵」と続きますが、特筆したいのが日本のこうじ文化の特異的な発展です。他国の多くは保存や栄養補強を目的とした発酵が主ですが、それらに加えてうまみにも焦点を当てているのが特徴です。世界の中でも繊細な味覚の持ち主といわれる日本人だからこそ、ここまで発展できたのでしょう。
今再注目の腸活に
こうじ菌は有効なのか?
腸内には無数の細菌が存在し、善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスが健康に深く関係しています。
こうじは、善玉菌のエサとなるオリゴ糖や、消化を助ける酵素を豊富に含むので腸の働きを自然にサポート。特に加齢とともに衰える消化・吸収力にとって、こうじ由来の酵素は心強い味方です。整腸作用の他、免疫力の維持や肌の調子、さらにはストレスや気分にも関わる「脳腸相関」への働きかけも期待されています。味噌や甘酒、塩こうじなど、毎日の食事で無理なく取り入れやすいこうじ菌。自然の力で整える食習慣で心身の健康を維持してみては。
参考資料:農林水産省ウェブサイト